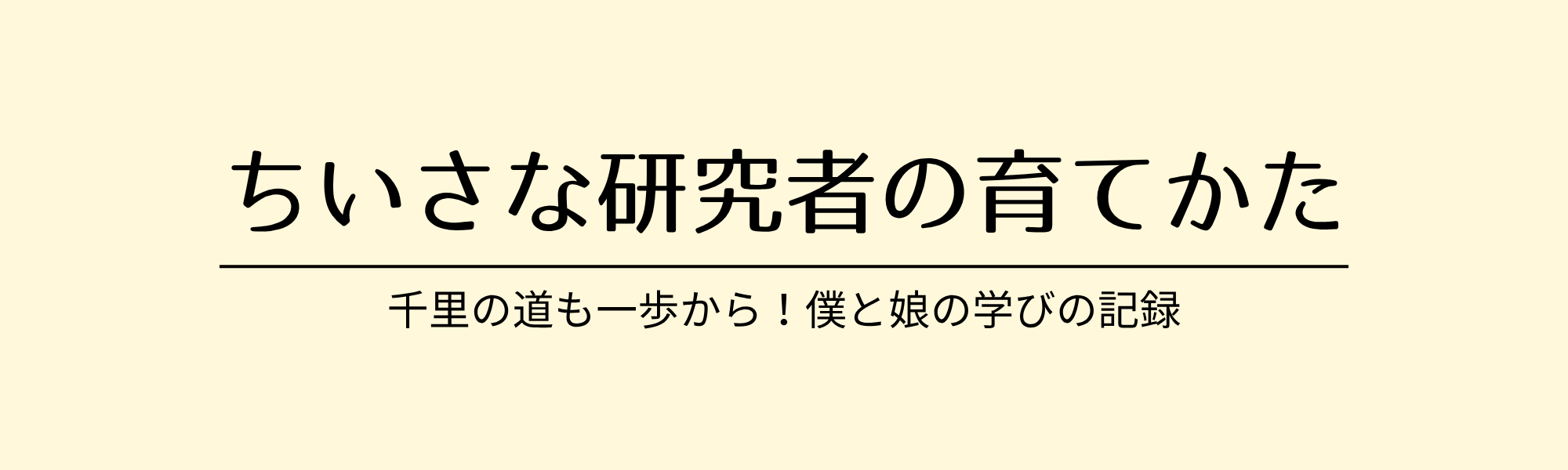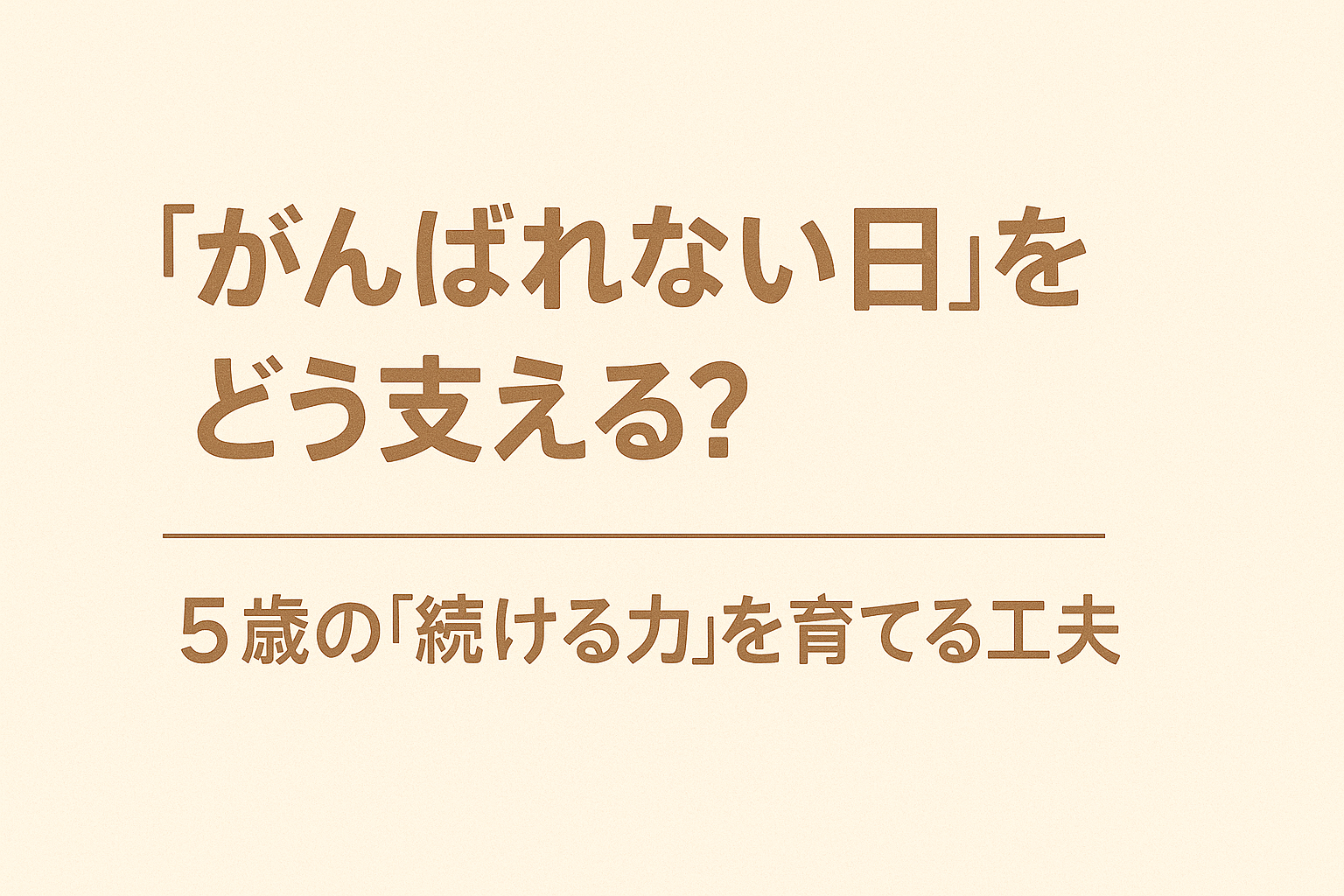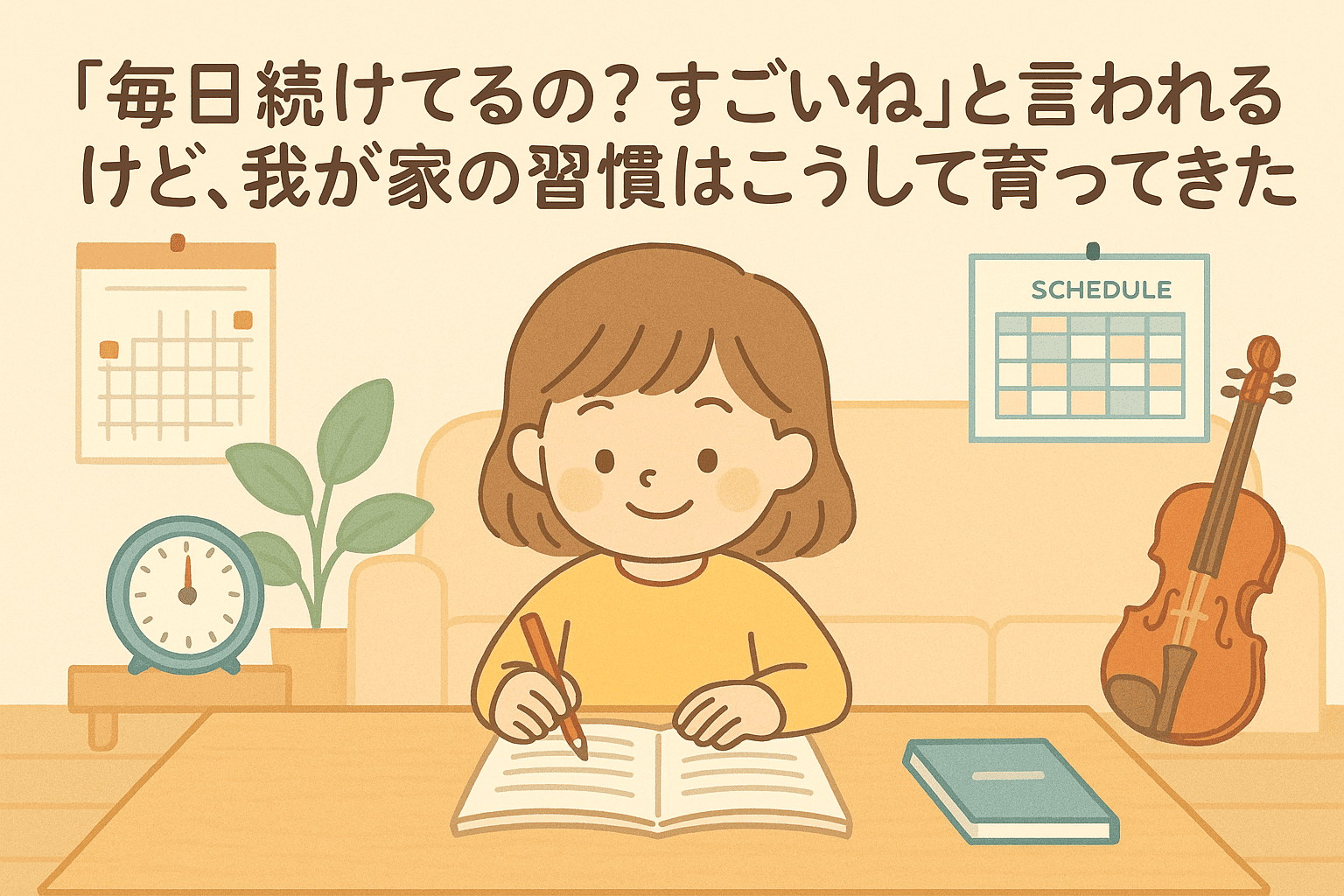✅ 導入|「がんばる」だけじゃ続かない
「毎日ちゃんと取り組んでいて、えらいね」と言われることが多い我が家ですが、
実は、すべてが完璧にできているわけではありません。
むしろ、“がんばれない日”があるのは当たり前だと思うようにしています。
娘はまだ5歳。気持ちや体調には波があり、
どんなに習慣化されていても、「今日は気分がのらない」「なんだか疲れている」日もあります。
そんなとき、無理にルールを押しつけるのではなく、
「がんばれない日」をどう過ごすかを一緒に考えることを大切にしています。
🌿 1. 「がんばれない日」も前提に入れておく
家庭学習や習いごとは、できるだけ予定通りに進めたいというのが親の本音ですが、
娘のコンディションに合わせて、できない日があってもいいと常に意識しています。
たとえば…
- 集中できない日 →「今日は先にごはんを食べてからやる?」
- イライラしている時 →「一度お水を飲んで、一緒に解いてみる?」
- 疲れている日 →「少し休憩してから始めようか」
こういった声かけは、娘の心に余裕をつくるだけでなく、
「困ったときは親が見ていてくれる」「助けてくれる」という安心感にもつながっていると感じます。
「一人でがんばらなきゃ」ではなく、“頼っていい”という感覚があるからこそ、自然にまたやる気が戻ってきているのかもしれません。
🎵 2. 声かけの“タイミング”を工夫する
ただし、毎回甘えさせてばかりでは、
本来なら乗り越えられた壁まで避けてしまうこともありました。
だからこそ、「がんばれない日」のサポートもバランスが大切です。
- できそうだなと感じた時は、「今日はもう少しがんばってみようか」と背中を押す
- 無理そうだなと感じた時は、「順番変えてみようか?」など工夫を提案する
ポイントは、親が勝手に判断して決めるのではなく、
選択肢を与え、子ども自身に決めさせること。
こうすることで、やるべきことは守りつつ、無理なく気持ちの切り替えができています。
💬 3. 「いつでも見ていてくれる」が安心感に
我が家では、娘の行動や努力をできるだけ具体的に言葉にして伝えるようにしています。
- 「最後の問題、苦戦したけど諦めなかったね」
- 「文字がとても丁寧だったね。書き順もバッチリ」
- 「昨日よりも計算が正確になってきたね」
こういった声かけで伝えたいのは、
「ちゃんと見ているよ」「気づいているよ」ということ。
それが、安心感につながっているようで、
最近では、親が隣にいなくても黙々と集中して取り組むことができるようになってきました。
🧠 4. 小さな成功体験が「またやろう」につながる
「がんばれない日」にも工夫して取り組み、やりきることができたときには、
- 「自分で決めたことを最後までやりきれたね」
- 「工夫すれば、できないと思っていたこともできるんだね」
と、“行動”や“思考”に目を向けた言葉をかけるようにしています。
娘自身も、「やってよかった」「ちょっと大変だったけど、やればできたね」と口にすることも。
誰にでも、くじけそうになる日はあります。
でもそれを「甘やかさない」で乗り越えるのではなく、一緒に乗り越える・寄り添うという姿勢が、
やがて自分で乗り越える力を育てていくのだと感じます。
🌈 まとめ|「がんばれない日」も学びの一部
子育てにおいて「続けること」は大切なテーマですが、
それは**「毎日完璧にやる」ことではない**と思います。
- 工夫する力
- 気持ちを切り替える力
- 親に頼ることができる安心感
そうした力こそが、「またやってみよう」という意欲につながっていると感じています。
我が家ではこれからも、
“がんばれない日”をどう乗り越えるかに寄り添いながら、
娘と一緒に、無理のないペースで続けていきたいと思います。