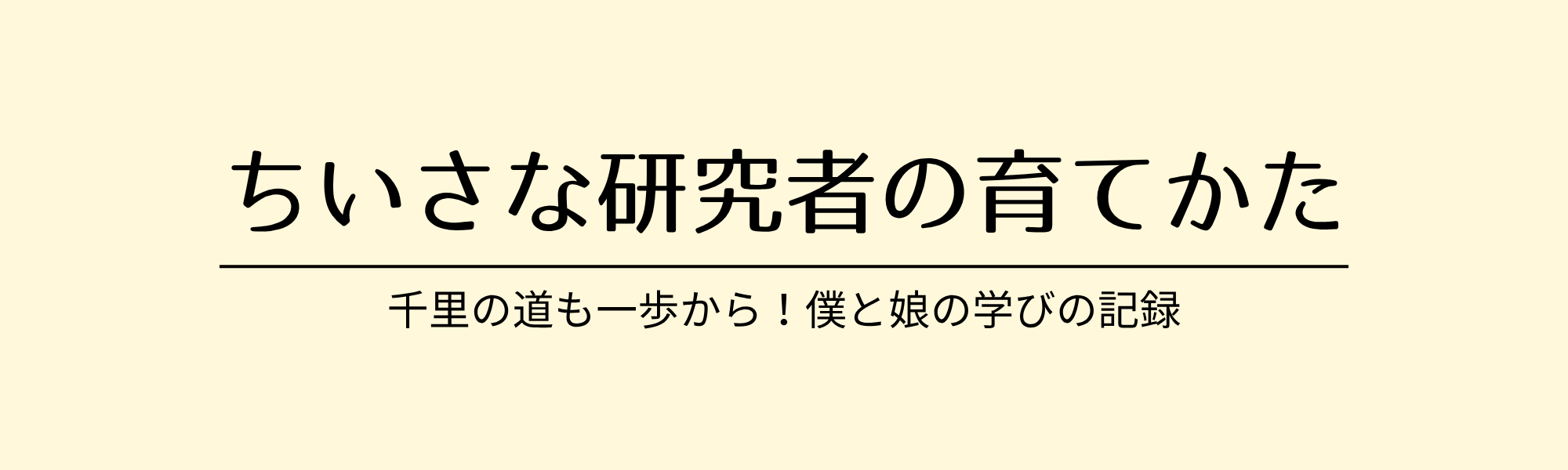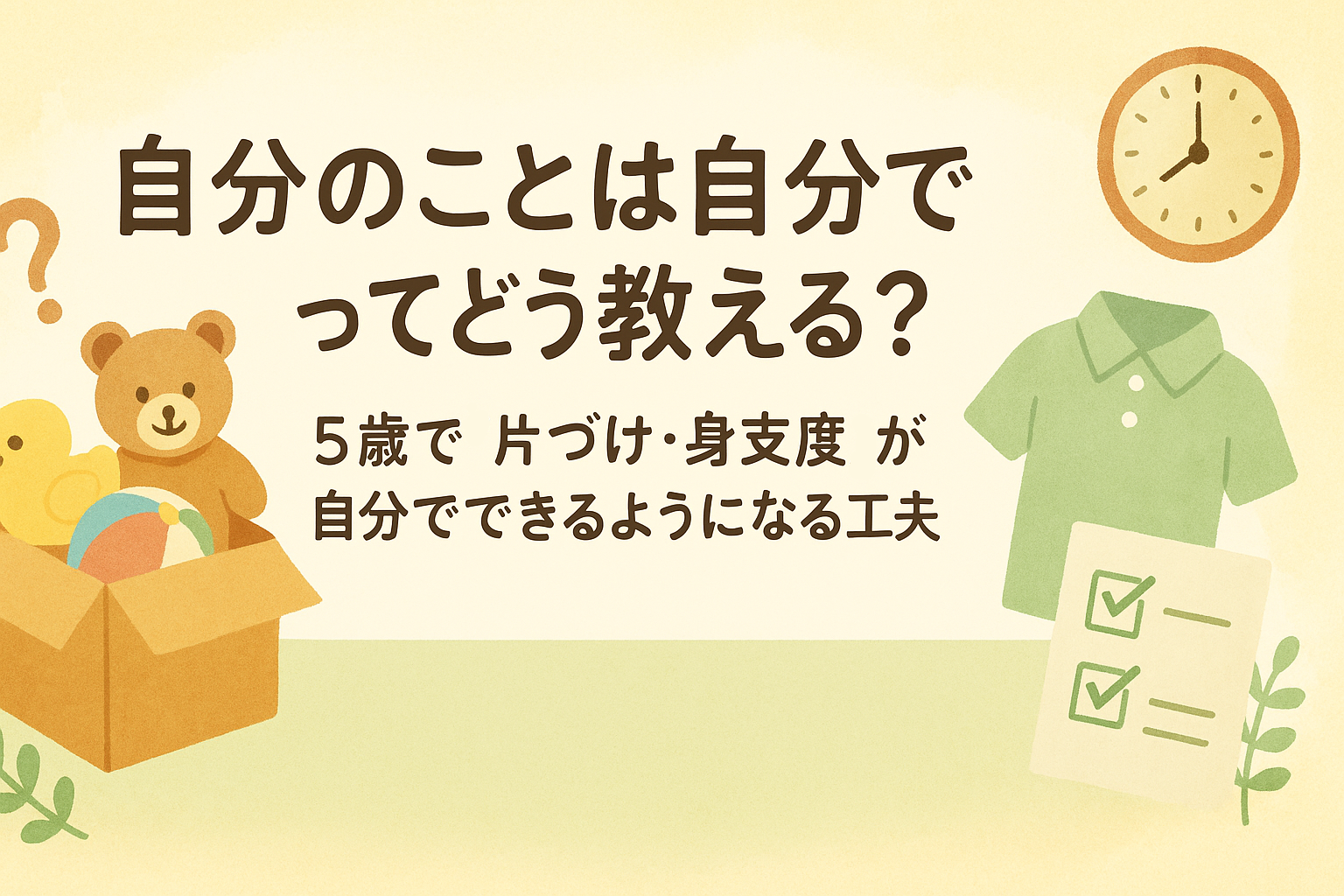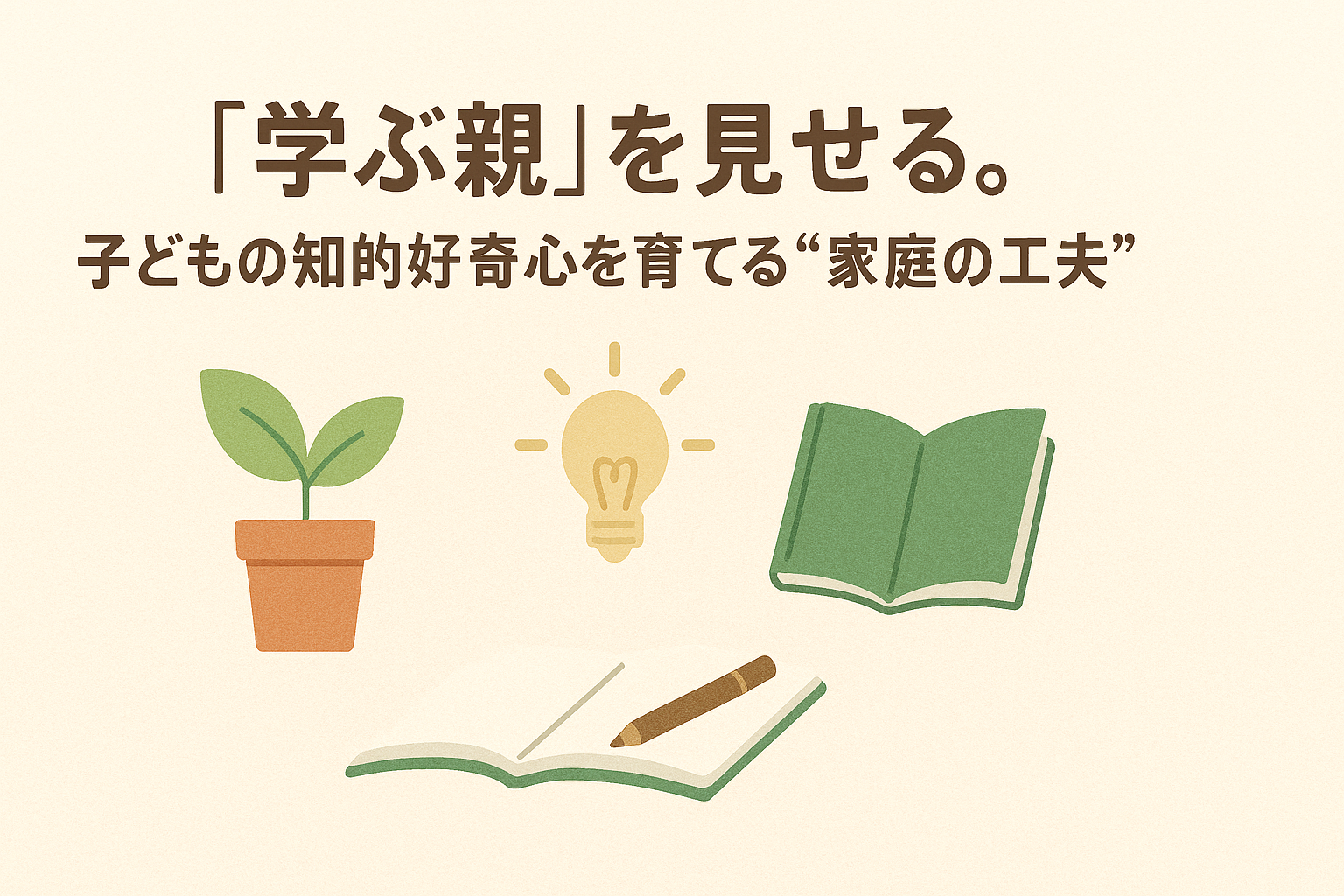✅ 導入|「自分のことは自分で」は5歳から少しずつ
「毎朝、着替えも身支度も片づけも、自分でやってるの?」「すごいね!」
そんなふうに声をかけてもらうことがあります。
もちろん、最初から全部スムーズにできたわけではありません。
でも、4歳ごろから少しずつ「自分のことは自分でやる」という意識を育ててきたことで、5歳になった今では、朝も帰宅後も、自分で行動を進められるようになってきました。
今回は、我が家で実践している「片づけ」や「身支度」を習慣にするための工夫をまとめてご紹介します。
🧠 1. 「指示しない」声かけで自分から動けるように
我が家では、朝の支度や帰宅後のルーティンにおいて、
「こうしなさい」「次はこれをやって」といった指示は基本的に出していません。
代わりに、
- 「今、やるべきことって何だっけ?」
- 「もうひとつ、やることあったような…?」
といった問いかけをするようにしています。
これにより、「次に何をすればいいか」を自分の頭で考えて、行動に移す力が少しずつ育ってきたと感じています。
⏰ 2. 「目標時間」を決めて、時計を味方につける
各行動には「目標時間」を設定しています。たとえば、朝の支度の際には、
「今日の目標、何分にする?」
と娘に聞き、だいたいいつも20分くらいでできるので、それより遅い時間を言ってきた場合は、
「〇〇ちゃんなら、もう少し早くできるんじゃない?」
と声をかけ、ちょうどよいチャレンジになる目標を一緒に考えています。
逆に、かなり早い時間を目標にすることもあり、そのときは、
「目標が高くていいね!じゃあ今日はその目標で進めてみよう」
と励ましながら進めるようにしています。
そして、進捗が悪そうなときは、
- 「目標時間、あと何分だったっけ?」
- 「何時何分って言ってたっけ?」
と時計を意識する声かけをしています。
こうしたやりとりを日々続けてきた結果、“分”単位で時計を読めるようになり、時間の感覚がぐんと育ってきました。
🧼 3. 帰宅後のルーティンも自然に定着
帰宅後は、「ただいま」→「手洗いうがい」→「今日の片づけ」→「明日の準備」までを、ほとんど自動的に進められるようになっています。
僕が何も言わなくても、家に帰ったらやることが流れとして身についていて、
その間に僕は夕飯の支度をしたり、持ち帰ったプリントを確認したりと家事を進めています。
これは、「親がラクをするため」というよりも、
“子どもが自分で動けるようになる力”を育てることを目的とした習慣づくりです。
🧺 4. “子どもができる環境”を整える
子どもが自分で行動できるようにするには、**親が教え込むこと以上に「できる環境を整えること」**が大切だと感じています。
我が家で実践しているのはこんな工夫です:
- 洋服や靴下などは子どもが取り出しやすい高さ・場所に収納
- 引き出しにはテプラでラベリングしてわかりやすく
- 持ち物の置き場所や支度の順番は一緒に話し合って決める
こうした工夫を積み重ねることで、「自分でできた!」という成功体験が増えていき、さらに自信につながっていくように思います。
💡 5. 親の準備こそカギ。「時間をかける余裕」を作る
忙しい朝や帰宅後、「時間がないから」とつい親が手伝ってしまいがちですが、
“時間がない”のは子どもではなく親の事情だと、我が家では考えています。
子どもが「自分でやる時間」を確保できるように、
- 夜のうちに翌朝の準備を済ませておく
- 少し早く起きて、余裕のある朝時間をつくる
- 焦らず見守れるよう、親の行動を前倒しする
など、親側の「段取り」こそがカギだと感じています。
🌱 まとめ|少しずつ手を離して「できた!」を育てる
子どもが自分で支度や片づけができるようになるには、時間と手間がかかります。
でも、4歳のころから少しずつ積み上げてきた習慣によって、5歳の今では、思っていた以上に自立して行動できるようになりました。
「自分でできた!」の経験を積み重ねることが、やがて自信や自主性につながっていくはず。
これからも、少しずつ手を離しながら、しっかりと見守っていきたいと思います。
✅ アクションポイントまとめ
- 指示ではなく問いかけで、自分で考える習慣を
- 各行動に目標時間を設定し、時計を読む力を育てる
- 帰宅後の流れは固定ルーティン化して、自然に習慣づけ
- 子どもが使いやすいように収納・環境を整える
- 子どもがゆっくりやるための時間的余裕は親がつくる