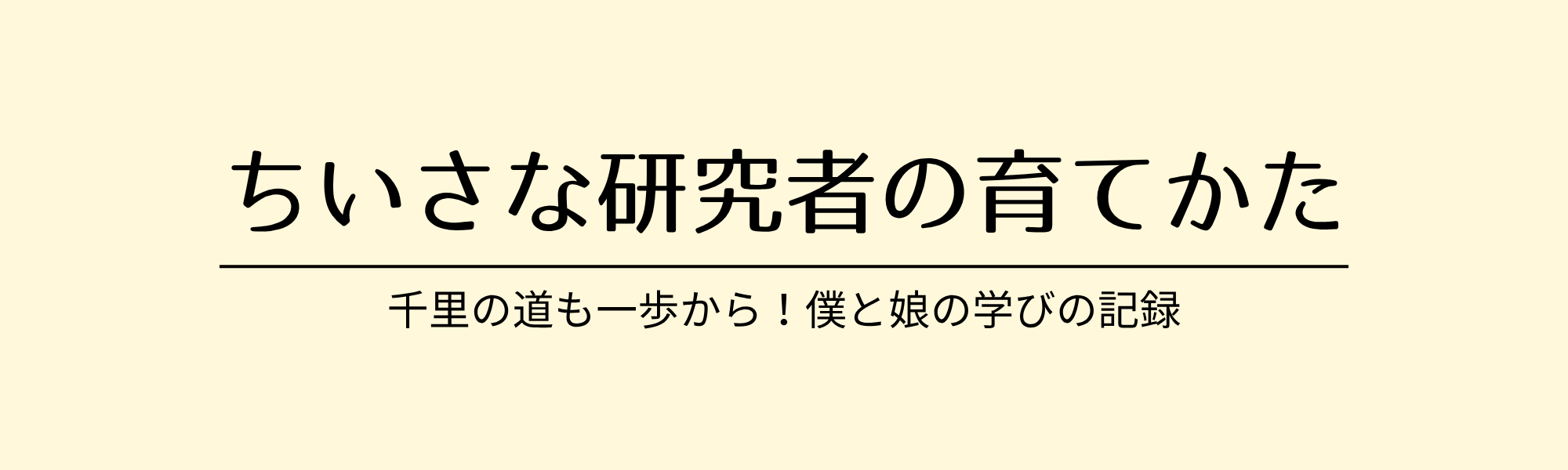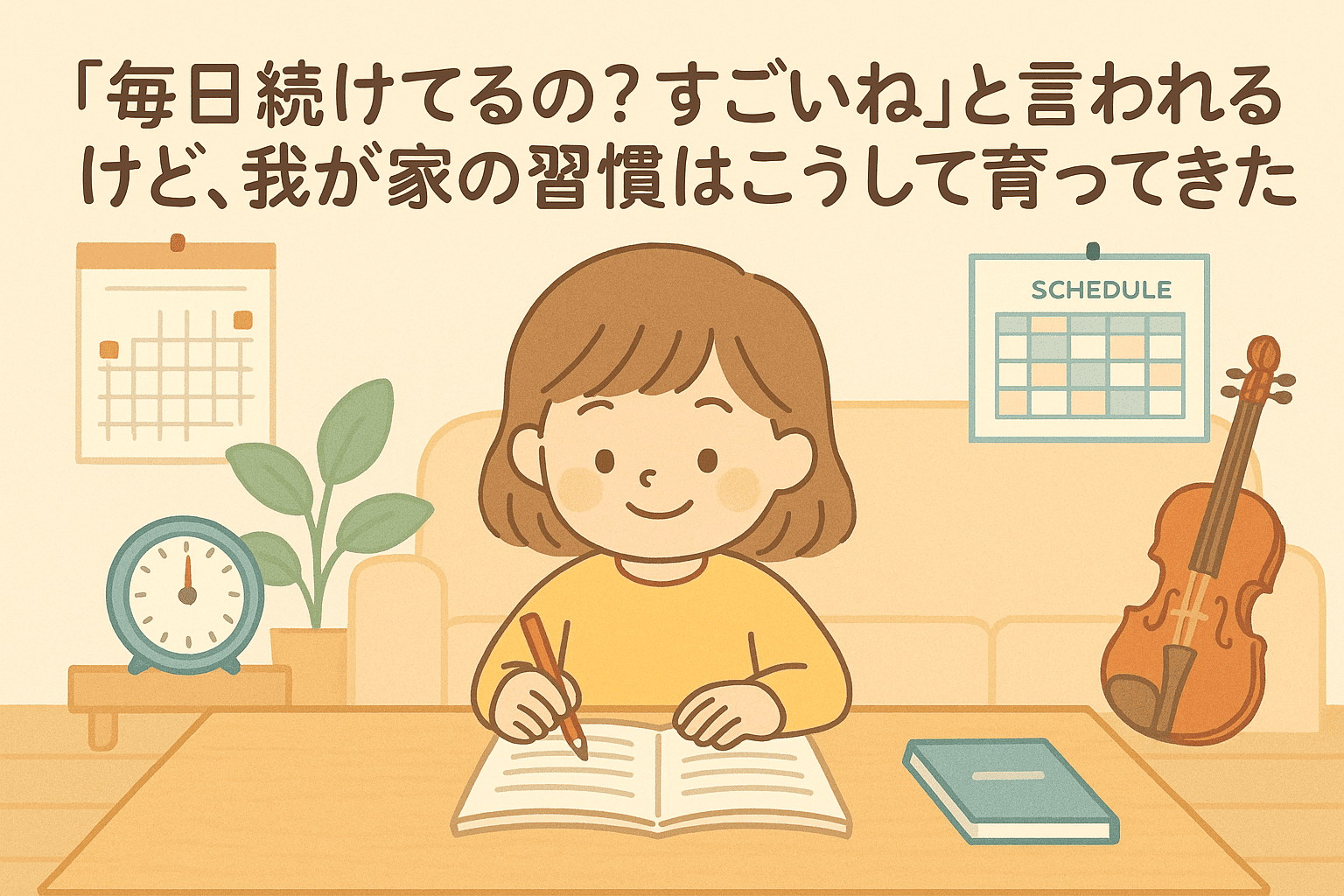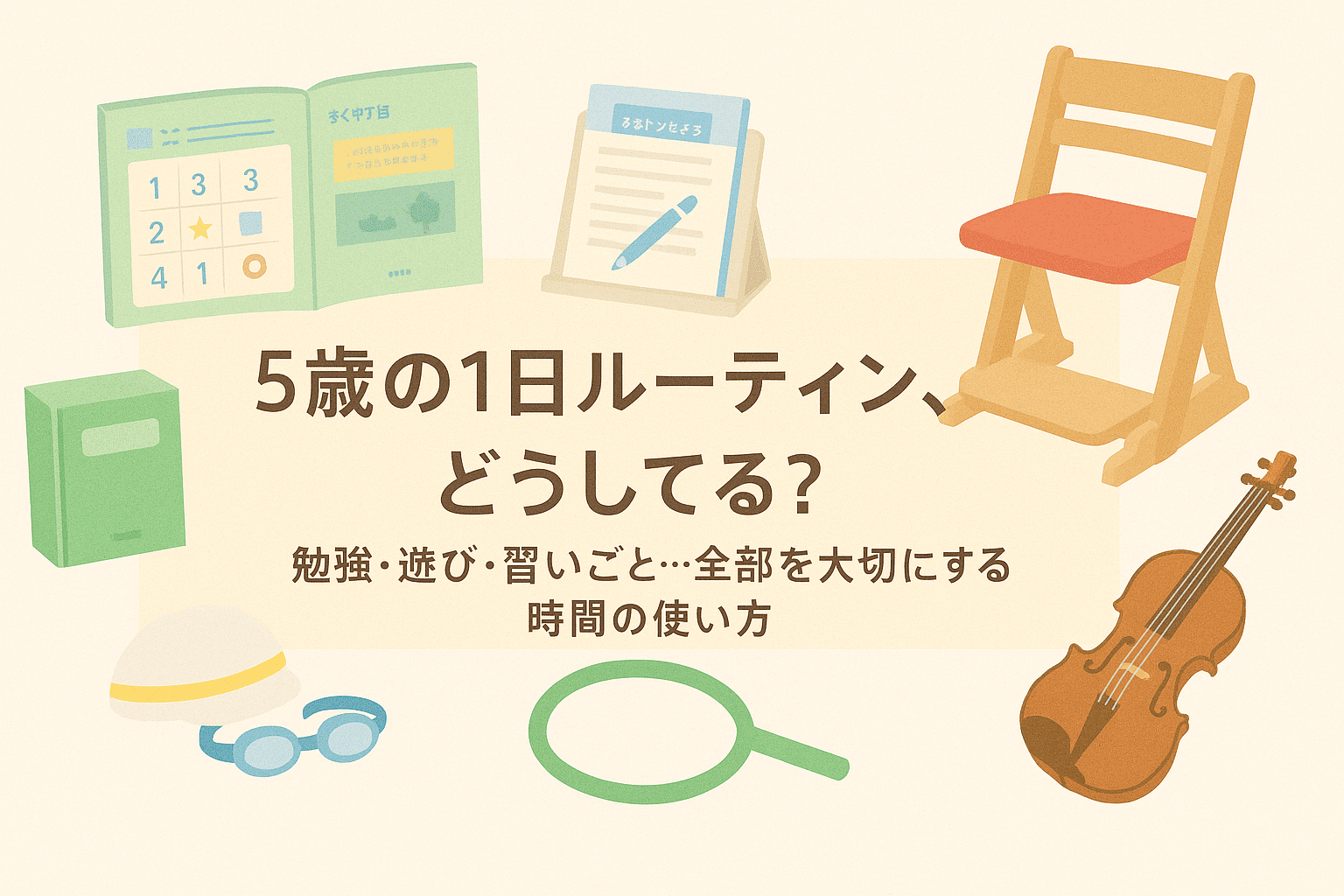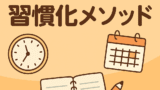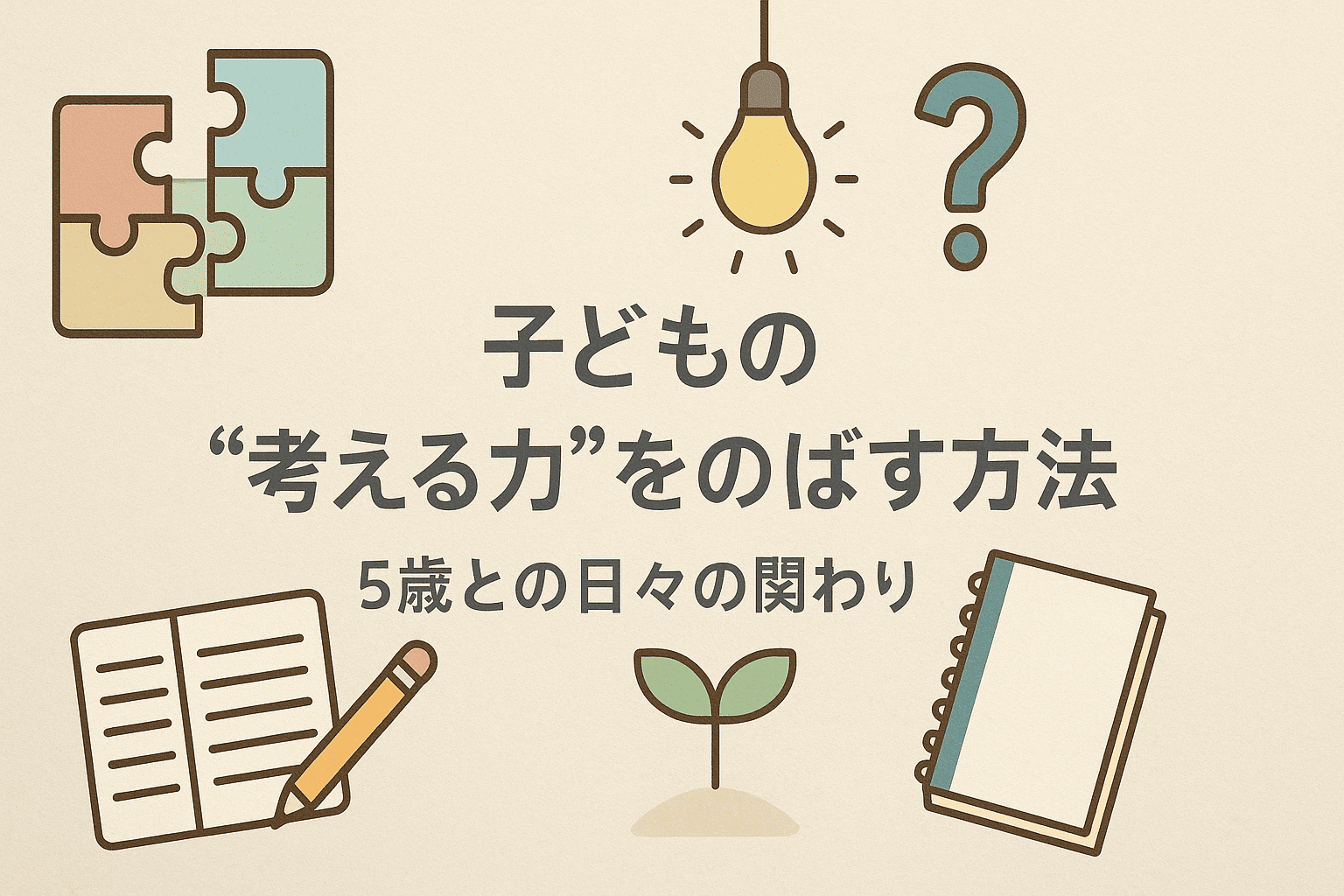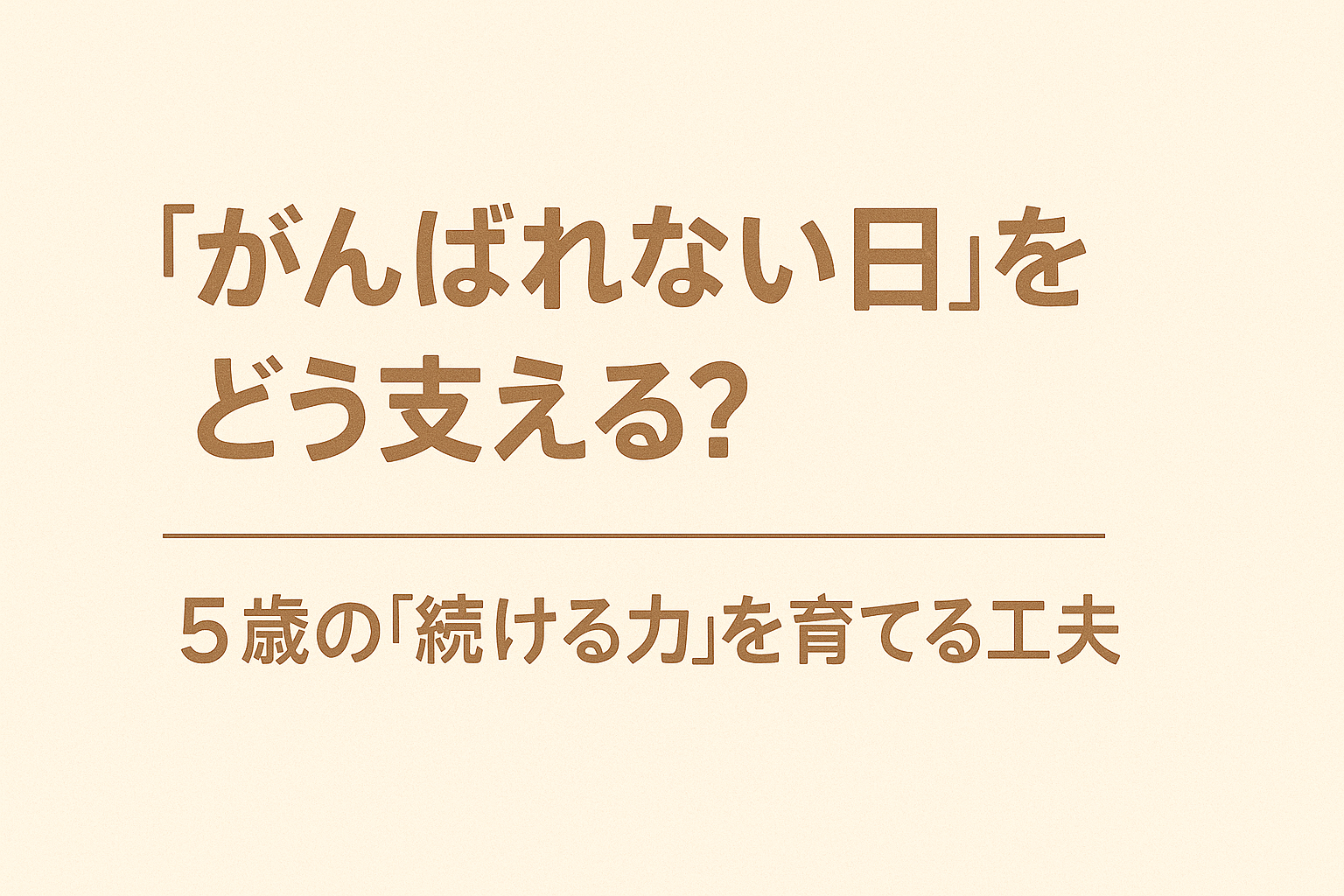「毎日バイオリンの練習してるの?」「プリント学習も毎日やってるの?」
周囲の方から、よくこんなふうに驚かれることがあります。
もちろん、毎日が完璧にうまくいっているわけではありません。でも娘は、4歳の頃からほぼ毎日、バイオリンや家庭学習にコツコツ取り組んできました。
今日は「どうして続けられているのか?」をテーマに、我が家で大切にしていることをまとめてみたいと思います。
👉“自分で決める経験”の大切さは、以前ご紹介した“やると決めたら最後まで”娘のやり抜く力の育て方でも詳しく触れていますので、ぜひそちらも読んでみてください。
🧩 1. 「自分で決めたこと」に責任をもつ
一番の理由は、娘に「やらされている」という感覚がないからだと思います。
バイオリンやスイミング、勉強の内容など、始めるときには必ず娘自身に決定権を持たせています。
たとえば、体験をした後には、
- 「楽しかった?」
- 「これからも続けたいと思った?」
- 「どうだった?」
と本人の気持ちを確認し、体験 → 選択 → 継続の流れを大事にしています。
「自分で決めたこと」だからこそ、途中でうまくいかないことがあっても心が折れず、少しずつ“やり抜く力”が育ってきたように感じています。
💬 2. プロセスに目を向ける声かけ
「今日も上達したね」
「集中して取り組んでいたね」
「昨日うまくいかなかったところができるようになったね」
これらは何気ない言葉ですが、「できた・できない」といった成果ではなく、“行動や努力”を認める声かけを意識しています。
プロセスに目を向けて言語化することで、娘も「今日はうまくできなかったけど、がんばったからOK」と前向きにとらえられるようになってきました。
毎日取り組むからこそ、小さな変化や成長にも気づけるのも大きなポイントです。
📅 3. “いつものこと”になるルーティン
我が家では、「いつ・どこで・何をするか」をある程度固定しています。
たとえば:
- 朝食前にプリント学習
- 夕食後にバイオリンの練習
- 寝る前に絵本を2冊
こうしたルーティンを生活の一部に組み込むことで、「やらなきゃ」ではなく「いつものこと」として定着。
取り組むまでのハードルが下がり、スムーズに始められるのも、継続の大きなポイントになっています。
「ルーティンづくりの工夫」については、こちらの記事でも紹介しています。あわせてご覧ください。
🧠 4. やめる勇気も継続の一部
毎日がすんなりいくわけではありません。
難しい問題や弾けない曲にぶつかって、泣きそうになる日ももちろんあります。
そんなときには、無理に続けさせず、
- 「今日はここまでにして、明日もう一回やってみようか」
- 「今日は別の曲を弾いてみる?」
と、クールダウンする時間をつくっています。
無理に続けさせるより、「今日もがんばった」と思える感覚を持たせることで、翌日のやる気につながっているように感じます。
🌱 まとめ|“続ける力”は日々の積み重ねで育つ
「続ける」って、子どもにとっても大人にとっても、簡単なことではありません。
でも、
- 自分で決める経験
- 認めてもらえる実感
- 続けやすい仕組みや環境
これらが整えば、少しずつでも前に進んでいける。
娘の姿を見ていて、そう実感しています。
👉「どうやって毎日の習慣が続いているのか?」という具体的な実践例は、こちらにも詳しく書いています。
「続ける力」は才能ではなく、日々の積み重ねで育つもの。
これからも、娘の気持ちやモチベーションを大切にしながら、寄り添っていきたいと思います。