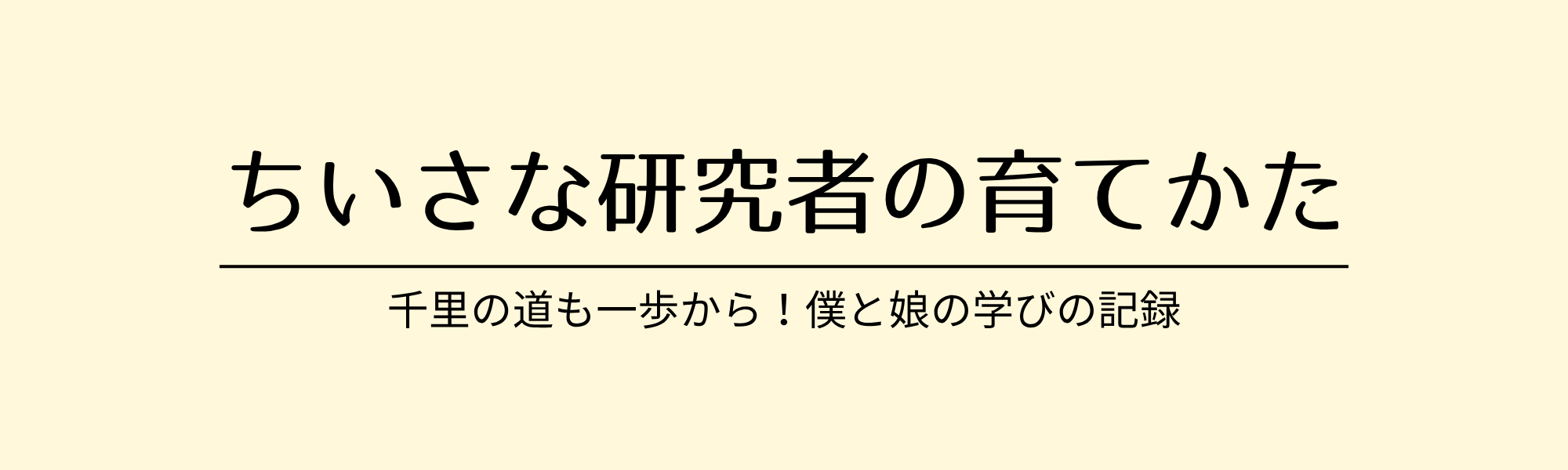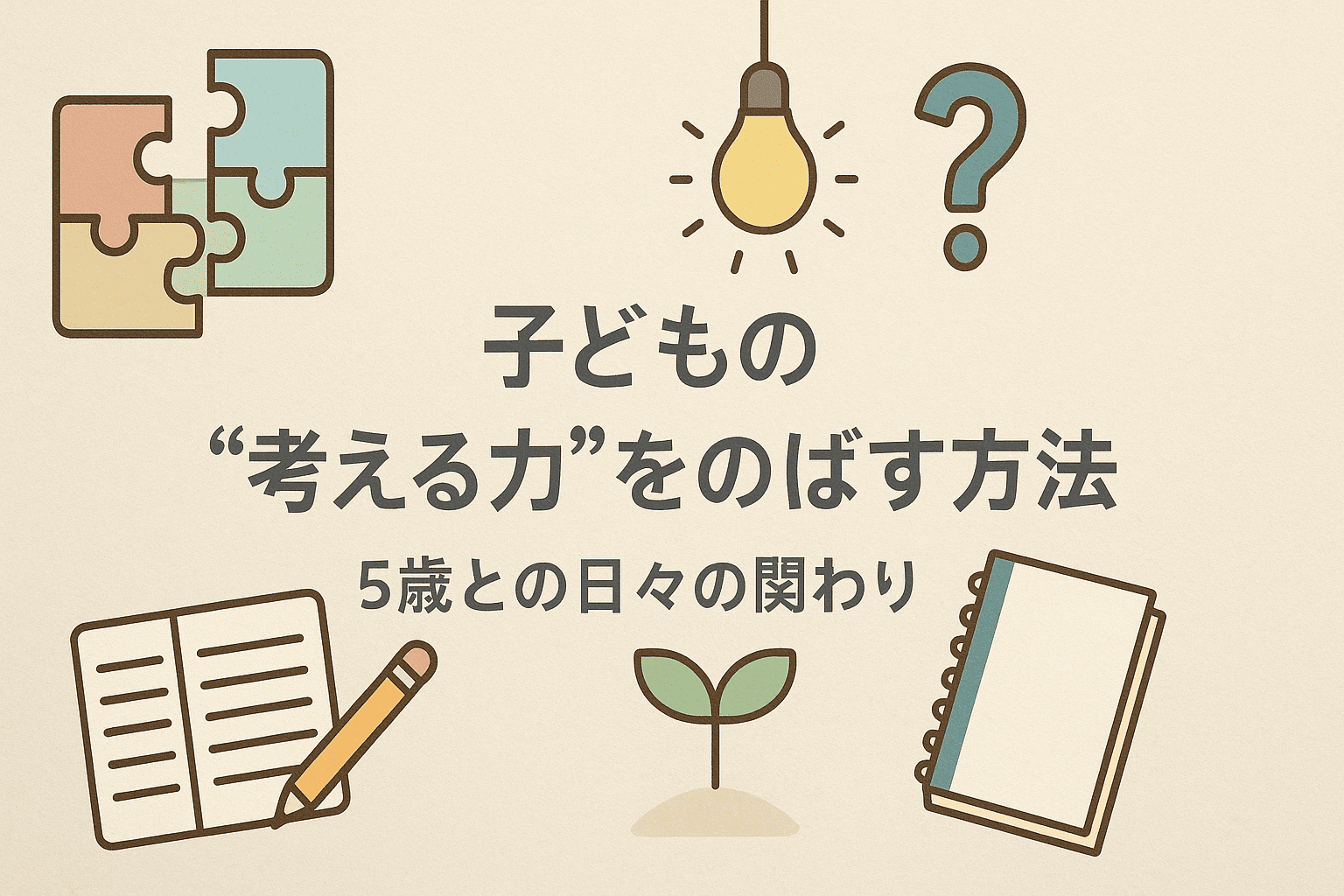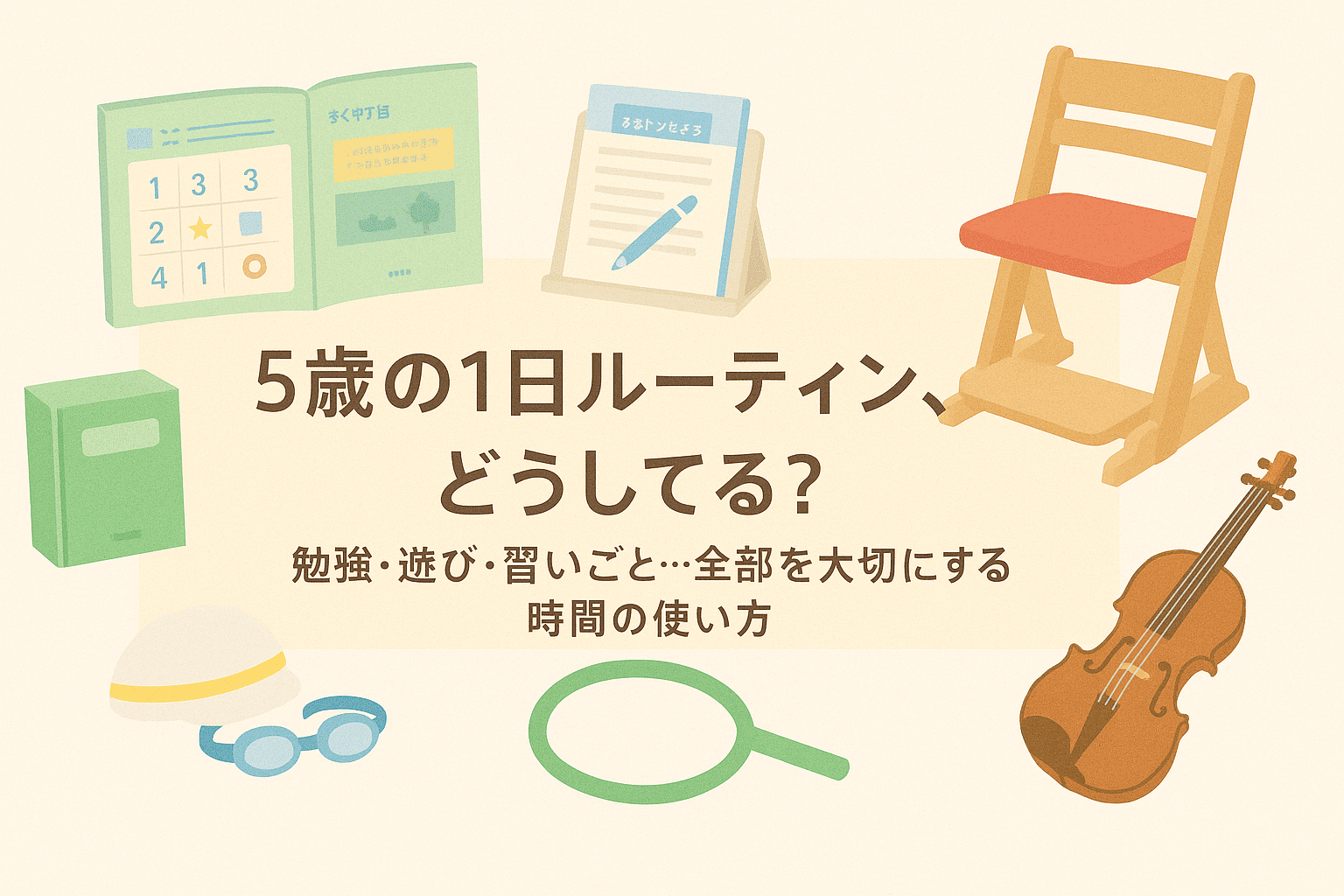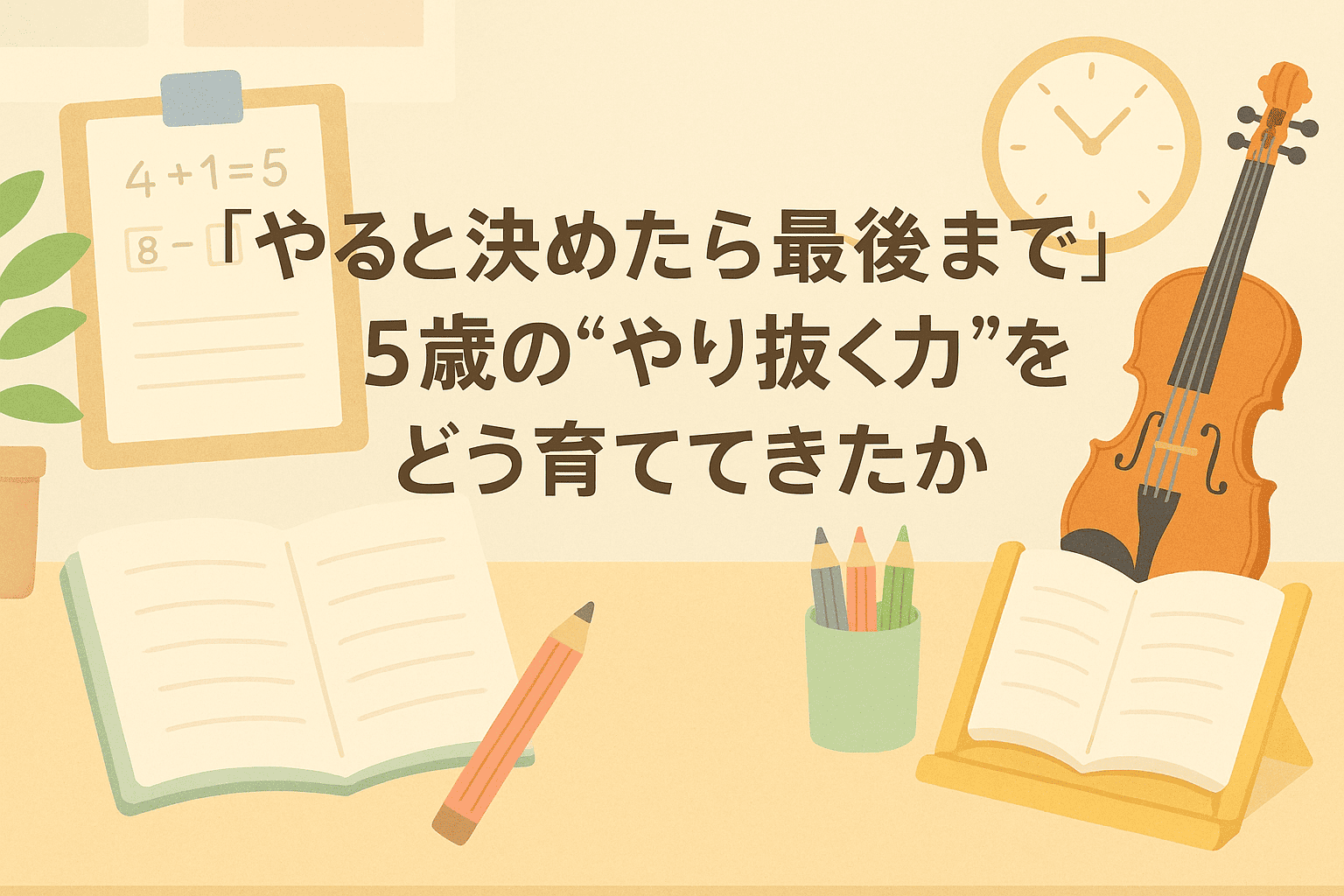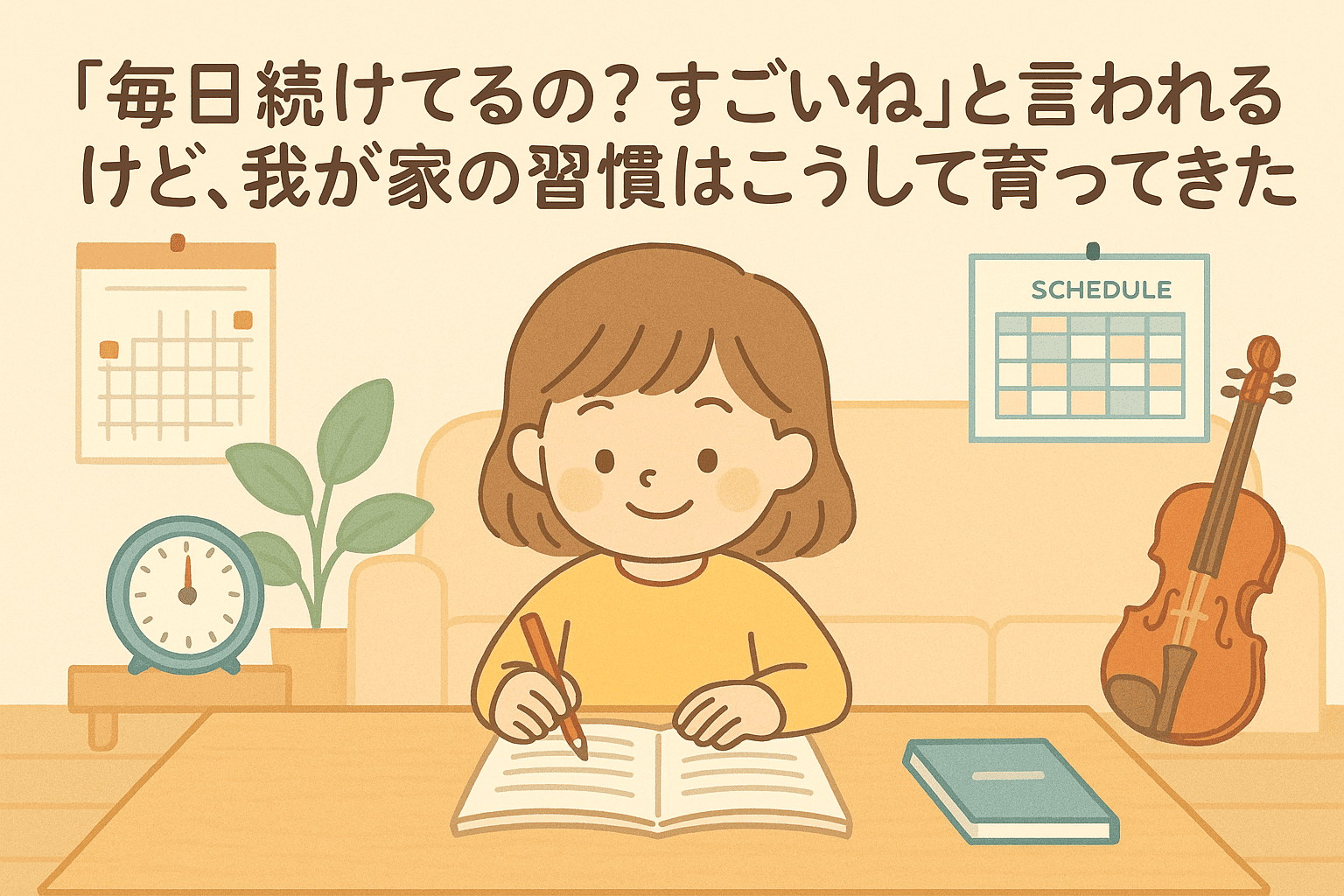✅ 導入:正解がない問いにこそ、「考える力」は育つ
我が家では、プリント学習や習いごとだけでなく、「自分で考える時間」をとても大切にしています。
「これって、どうしたらいいんだろう?」
「なんでそうなるの?」
こんなふうに、正解がひとつではない問いに出会ったとき、子どもの思考力はぐんと伸びると感じています。
🧠 1. 教えすぎず、問いかけでサポート
すぐに答えを教えるのではなく、
「どう思う?」「なんでそう考えたの?」と問いかけるようにしています。
たとえば、ひらめきが必要な問題では、現実のものに例えたり、必要なパーツを手作りして手に取れるようにすることで、娘自身の中にある“考えるヒント”を引き出せるよう工夫しています。
その結果、「考える時間を繋いでいくこと」が自然とできるようになり、粘り強く取り組む姿勢にもつながっています。
🌼 なぜなぜ期に、とことん付き合ったこと
娘は3歳ごろから、「なんで?」「どうして〇〇なの?」と、わからないことをどんどん質問するタイプでした。
特に小さい頃は、同じことに対して何度も「なんで?」と聞かれることが多く、回答するのも正直大変な時期がありました。
それでも「この前教えたよね?」のような反応はせず、毎回初めて聞かれたように答えることを意識していました。
その影響もあってか、今でも「どうして?」「なんで?」と疑問を持つことが自然になっているように思います。
✨ 2. 「考えたプロセス」を認める
正解かどうかではなく、
- じっくり考えた時間
- 自分なりの工夫のあと
- あきらめずに取り組んだ姿勢
こうしたプロセスを具体的な言葉で認めるようにしています。
たとえば、
「今の考え方、いいアイデアだね」
「いろんな方向から考えることができたね」
このような声かけを重ねることで、
「考えることがしんどい」「難しい」ではなく、自然なこと・嫌じゃないことというイメージがついてきたように思います。
💭 3. 答えがひとつじゃない問いにも慣れる
家庭内の会話でも、「どっちがいいと思う?」「どうしてそう思ったの?」など、正解のない問いを意識して日常に取り入れています。
たとえば:
- 「なんでこの蝶はここに飛んできたんだろう?」
- 「大きくなったら、どんな人になりたい?」
- 「梅雨はなんでたくさん雨が降るんだろうね?」
こんな問いかけを通して、**「自分の考えを持つ → それを言葉にする」**という練習になっていると思います。
🌱「自分で考える力」を育てるには、日々の習慣づけも重要です。
🔽「毎日のルーティン」に関する記事もあわせて読んでみてください。
🌱 4. 「わからない」を受け入れることも学び
難しい問題や質問に直面したとき、すぐに答えが出ないこともあります。
そんなときは、
「いくら考えてもわからないことってあるよね」
「また今度一緒に考えてみようか」
と、無理に答えを出さずに途中で終えることも。
「わからないままでも大丈夫」
「すぐに正解にたどり着かなくてもいい」
そう伝えることで、考えることそのものをポジティブに捉える力が少しずつ育っているように感じます。
📝 まとめ|“答えのない問い”が、思考力の土台をつくる
考える力は、知識の詰め込みだけでは育ちません。
問いを楽しみ、プロセスを認める経験の積み重ねが、土台になると思っています。
我が家では、教材選びや日々の声かけ、会話の中で「考える楽しさ」に触れられるよう工夫しています。
これからも、正解だけを求めず、「どう考えたか」に寄り添う子育てを続けていきたいと思います。